籐家具とは?籐家具の選び方や手入れ方法もご紹介!
「籐家具はどのような魅力があるのだろう」「籐家具は何を基準にして選ぶのだろう」上記のような疑問を抱えている、籐家具の購入を検討している方も多いのではないでしょうか。籐家具は、天然素材の籐を使った温かみのある家具です。耐久性があるため長く愛用することが見込まれ、使い込むほど味が出ます。その一方で天然素材のため品質にバラツキがあり、選び方が難しいです。本記事では、籐家具を検討している方に向けて、籐家具の魅力や選び方、手入れ方法、籐の特徴について解説いたします。
籐(ラタン)とは

籐家具で使われている籐とはどのような種類があるのでしょうか。耐久性や使い勝手がよい籐の種類や原産国を見ていきましょう。
種類
籐は4種類あり、それぞれに特徴があります。
丸籐
直径5㎜~15㎜あり、皮がついたままの籐の素材です。とくに材料「セガ」は、表皮が半透明のほうろう質で美しい光沢を持ち、日本では最上品種として高く評価されています。
皮籐
丸籐の皮を挽いた中身の部分であり、籐を割って皮の部分を一定の幅と厚みに調整した素材です。このヒモ状の材料は、主に巻いたり、編んだりする際に使われます。
丸芯・半芯
丸籐の皮の部分を挽いた中身の素材です。この素材は艶があり、繊維がつまっていて耐久性に優れており、最高級の素材とされます。柔らかさもあるため、編みやすいです。また、籐の表面は丁寧に加工されており、ささくれが最小限に抑えられています。
大民・中民
直径15㎜以上の太い籐で、家具のフレーム材料として利用されることが多いです。柔軟性に優れ、丈夫なことが特徴です。
原産国
籐は、主に東南アジア一帯や南米、アフリカ、スリランカなどで産出される素材です。その中でも、とくにインドネシアは主要供給国であり、世界の籐資源の80%を保有しています。インドネシアの籐は、産業素材として非常に優れており、強度と加工性があります。また、籐の原材料の輸出だけでなく、製品としての加工も盛んで、完成品の輸出も重視しています。
籐家具の魅力
籐家具は、耐久性や使い勝手がよい籐を使用した天然素材の家具です。具体的にどのような魅力があるのでしょうか。
軽い
軽さが特徴的であり持ち運びが容易なため、高齢者にも扱いやすく、掃除や部屋の模様替えも手軽に行えます。素材の籐は軽くて丈夫な上に、柔らかさも持ち合わせています。自由な曲げや編み込みが可能で、家具の背もたれなどに使うと、体に合わせて程よくしなり、快適な座り心地を感じます。
耐久性がある
籐家具は耐久性に優れており、こまめな手入れによって何世代にもわたって使用が見込まれます。手入れ方法については後に説明いたします。
四季に合わせて使いやすい
夏の暑さや冬の寒さに合わせて使うことが見込まれます。籐の表面は熱伝導性のよいホーロー質に覆われているためです。夏には、湿気を籐の繊維の内側に吸収し、常にサラッとしたひんやり感があります。そのため、汗を気にせず快適に過ごすことができます。とくに籐素材の椅子やソファなどは心地よく、薄着の季節にぴったりの家具としておすすめです。また、天然素材ならではの暖かみがあるため、冬の寒い時期にもおすすめです。北海道などの寒い地域でも人気があり、一年を通して愛用されています。
天然素材のぬくもりを感じられる
天然素材100%の籐家具は、熟練の職人が一つひとつ手作りしています。そのため、天然素材が持つ繊細な質感とナチュラルな色合いが調和され、暮らしや装いに馴染みます。使い込むほどに独自の味が出るのも魅力で、経年により深みのある飴色に変化していくことで愛着が増していきます。
籐家具の選び方
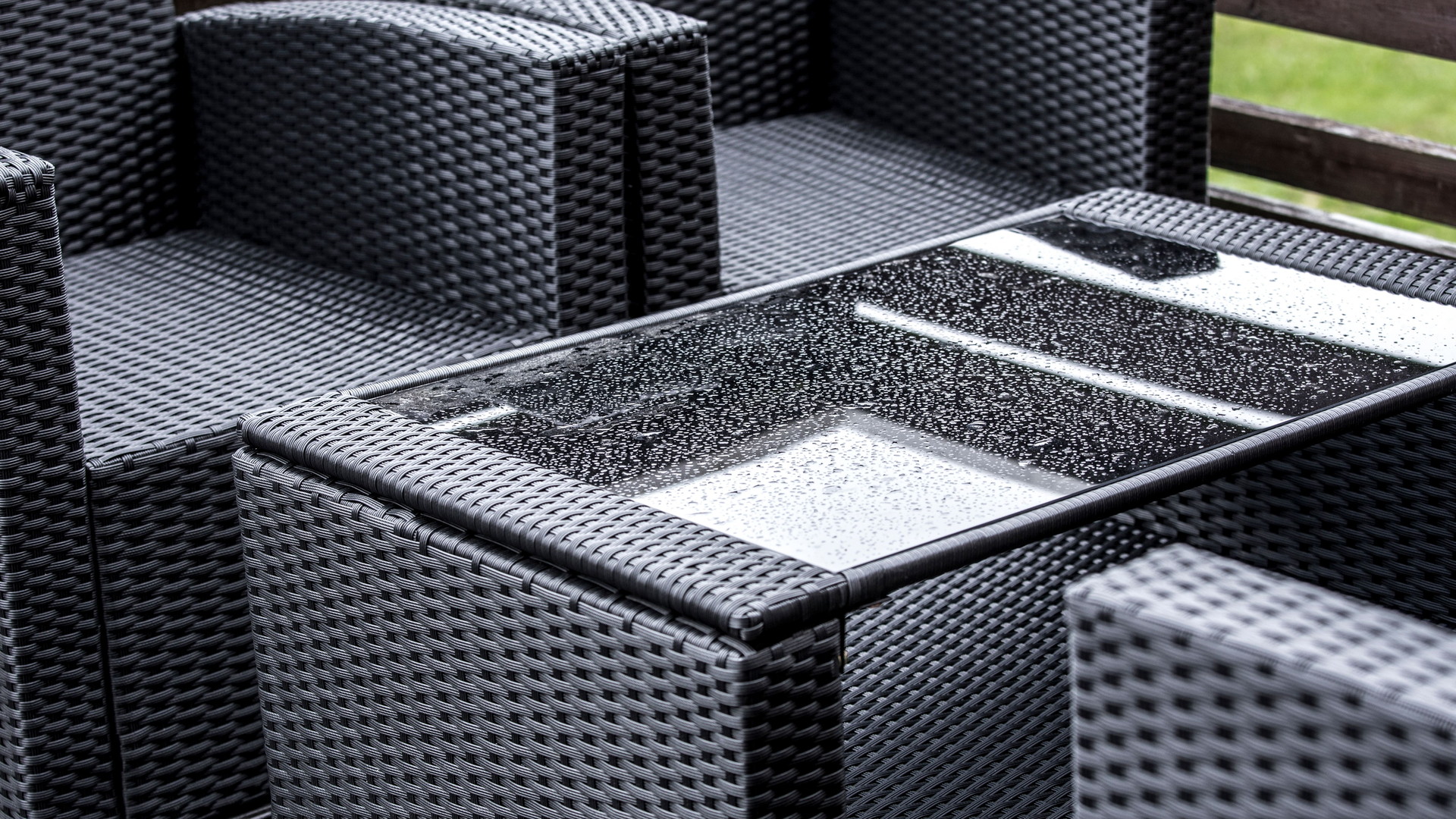
籐家具を選ぶ際のポイントは以下のとおりです。
感触で選ぶ
籐家具を選ぶ際には、触った時の感触が重要な指標です。籐は天然素材のため、品質にバラツキがあるからです。ザラザラした感じがある場合は、品質があまりよくない可能性があります。また、籐家具のフレームをはじめ、各部位(座面や背もたれなど)の接合部にも注意してください。接合部にほつれやささくれなどが見られる場合は、製造過程で雑な処理がされている可能性があります。
塗装やニスの仕上がり具合で選ぶ
籐家具の塗装やニスの仕上がり具合は商品により異なります。きちんと確かめて、自分の好みに合ったものを選びましょう。
サイズで選ぶ
使いやすいサイズを選ぶことです。配置を事前に決め、必要な家具の高さを把握しておくことが大切です。これにより、お部屋にぴったり合った家具を選ぶことが見込まれます。これらのポイントを踏まえて、よい籐家具を選べます。外見だけでは分からないので、実際に実物を手に取って確認することが大切です。実店舗で籐家具の感触を確かめ、その後はインターネットで購入するという方法もおすすめです。
籐家具の手入れ方法
籐家具は耐久性があり、日ごろの手入れで何年も使用することが見込まれます。ではどのように手入れするのでしょうか。
ほこりを取る
籐家具の手入れは簡単で、普段は乾いた布で乾拭きし、小型のブラシやほうきでほこりを取り除くことが見込まれます。べとついた汚れの場合は、ぬれ雑巾で拭くことも見込まれますが、常にぬれた雑巾で拭くと艶がなくなる可能性があるので注意が必要です。家庭用中薄めた性洗剤を柔らかめの布につけ、軽く拭き取ります。あとは乾いた布を用いて、洗剤と水気を丁寧に拭き取ります。このとき、特殊な洗剤やワックス、シンナーなどの使用は避けましょう。水洗い後は陰干しで乾燥させてください。
艶を出す
毎日使っていると、艶がなくなり乾燥いたします。年に1回の頻度で、艶出しの手入れをしましょう。以下の手順で行います。
水で濡らして固く絞った柔らかい布で表面のホコリや汚れを取る
一度しっかり乾燥させる
布にオイルを取り、籐に馴染むように塗る
細かく塗り、20分ほど放置する
乾いた新しい布でオイルを拭き上げる
適度な保湿する
これらの手入れを行うことで、籐家具は美しさと耐久性を保ち、長く愛用できるでしょう。ラッカースプレーを使うと艶が出るのできれいな仕上がりになりますが、屋内での使用は溶剤が充満するため危険なので、屋外で行ってください。
通気のいい場所に置く
籐は天然素材で、乾燥や直射日光を避ける必要があります。冬は暖房の風が当たる場所、夏は湿度の高い場所を避けるようにしましょう。とくに過度な乾燥や日光の影響により、籐が割れたり変色したりする可能性があります。また、湿度が高い場所でも籐は敏感に反応いたしますので、通風や換気を心掛けましょう。
負荷をかけない
籐家具の編み込み部分は繊細で、物置や踏み台などに使用することは避けるべきです。一点に加重がかかると、編み込み部分が破損することがありますので注意してください。籐家具を長く美しく使うためには、優しく取り扱い、過度な力をかけないよう心がけることが大切です。
まとめ

籐家具は天然素材ならではの質感、さらには色合いにより、使い込むほど自然に馴染んでくれます。夏には汗を気にせず快適に過ごすことができ、冬には暖かみを感じることが見込まれます。また、耐久性があるため、日ごろの手入れで何年も使用することが見込まれます。たとえば定期的にほこりを取り、1年に1度艶を出すことです。過度な乾燥や日光の影響により、籐が割れたり変色したりする可能性があるため、通気のよい場所に置くことも重要です。